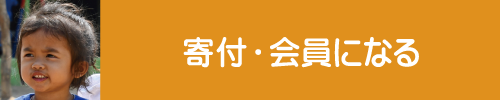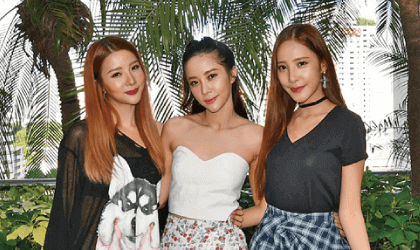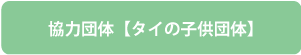CHANGレポート カンボジアの孤児院
孤児院に対する政府の指導
2019年4月:カンボジア
孤児院のオーナーとなって約3年、とにかく大きな変化としては、政府の孤児院に対する方針と指導でした。
2017年の暮れあたりから、行くたびに子供が減っていくのです。
ママに尋ねると「ちょっと親戚の家に行ってるだけだよ」と言われたので、当初は特に気にしていませんでした。
しかしこれはママが私たちに心配かけないように言っていただけだったのです。
この頃、政府は「親や親戚がいる子はそこで生活すること」という方針になり、強制的に次々と子ども達を身内のもとへ帰していたのです。
身内のもとで生活することで、その子が本当に満足なら納得できます。
しかし、そこでは育てることができないから保護していた子供が殆どなのです。
そして2018年6月にママが突然亡くなりました。
この頃から政府の指導はより強いものとなりました。
当初37人いた子供は、この頃10人ほどにまで減ってしまいました。
私たちはとても心配で、とても寂しく何度も政府との話し合いを求めました。
そして2018年9月、話し合いの場がやっと実現したのです。
こちらからの参加者は、私たちと孤児院のパパと現地スタッフ、村長や近所の語学学校の代表も参加してくれました。
そして政府側も5人もの担当者が来てくれました。

政府の役人は、1年以上この孤児院にほぼ毎日訪れて、運営をチェックしていました。
その結果、以下のようにこの孤児院は、安全面、衛生面、管理面で子供を保護するのに適していないということを筆頭に、たくさんの指摘がありました。
- 孤児院の門と塀が崩壊していて、見知らぬ人が勝手に孤児院の中に入ってきている。
- 踊りや劇の練習、イベントへの出演が多すぎる。学校と勉強を最優先にすべき。
- 子ども達の通常の生活と、学校と勉強を最優先にするべき。
- 訪問者への対応が多すぎる。子ども達の通常の生活を最優先にすべき。
- 子ども達の部屋に鍵がない。
- 男女別のトイレとシャワーがない。
- 村にドラッグをやっている人もいるので危険。
- この人数の子供を管理するなら常勤のスタッフが5人以上必要。そしてスタッフはボランティアではなく、有給でないといけない。
- パパが病気で亡くなったら、誰が子供と一緒に暮らすのか。
- 子供を預けることを親や親戚が認める書類がない。
- 子供が脱走したり、悪いことをしたら誰が責任をとるのか。
- 孤児院と大家との契約期間が短かすぎる。長期契約が必要。
- 以上から、先ずは引越しするべき。引越し先は2,000m²以上の土地があること。
- 引越し先の施設はコンクリート造りであり、外部の人が入ってこれない厳重な門と塀が必要。
- 日本人がオーナーならデポジットを考えてほしい。1年間3,000$くらい。
他にも多々ありましたが、このような指導と条件が出されたのです。
そして「これができるなら応援しましょう」ということでした。
これは政府の担当者が感情的に言っているのではありませんでした。
担当者は分厚いマニュアルを見ながら、時に私たちにも見せてくれながら説明していましたので、正式な政府としての方針なのです。
その日のうちに、先ずは大家に「あと何年契約ができるか?」を聞きに行くと「あと1年半です。それ以上は貸せません。」ということで、この施設に長くいられないことが分かりました。
そして翌日は2,000㎡の土地を何ヵ所か見に行きました。
そんな広い土地を借りるには大変な金額が必要です。
何とかなるような場所もありますが、そこは遠い郊外、学校もお店もないような場所で生活することはできません。
更に土地の問題だけでなく、コンクリート造りの施設や2,000㎡を囲む厳重な塀を造るにも、かなりの資金が必要となります。
結果として政府の求めるほどの場所に移転することは不可能と判断しました。
ただ驚いたことに、政府は強制的に子ども達を帰し、それっきりではありませんでした。
その後の管理もしっかりとしてくれていたのです。
私たちが子ども達の心配、会えない寂しさを伝えると「どの子ですか?」と聞いてきます。
私が名前を挙げると、直ぐにスマホから写真を見せてくれました。
「この子ですよね。今は叔父さんの家で暮らしていますよ」と、叔父さん達の家で幸せそうにしている写真を見せてくれたのです。
そして次々と子供の写真を見せてくれます。
私が名前を挙げて分からない時は、「その子は担当が違うので」と役所に電話、すると別の担当者から直ぐにLINEでその子の写真が届くのです。
政府は基本的に毎月のように子ども達の様子を見に行ってくれていたのです。
定期的に子供の家に訪問して、健康状態をチェック、ちゃんと学校に行っているか、虐待とか受けていないかなど、確認してくれていたのです。
私たちにも「孤児院で育てる以外にも方法はあるでしょう。私たちと一緒にいつでも子ども達に会いに行きましょうよ。日本にいるから行けないなら、私たちに文房具とか渡してくれればちゃんと届けますよ。生活や教育費が心配なら50$くらいのお金なら渡してもいいですよ」と、一緒に訪問することを提案してくれて、協力してくれることも言ってくれたのです。
私たちは実際に政府の人と会うまで、敵対視していましたが、何度も会って話をしてみると、想像していたような冷たい方針や態度ではありませんでした。
この対応には本当に安心しました。
「確かに政府の言う通り、孤児院だけに拘る必要はない」と思うようになったのです。
そして更に、政府からの提案として「大々的に孤児院をやるのではなく、村のコミュニティとして運営したらどうでしょう」と言われました。
コミュニティとは、子ども達が学校に行く前後や休日にご飯を食べたり、遊んだりできる場所です。
元々うちの孤児院の庭は村の子ども達に開放していたので、そのコミュニティを前面に出して運営するという提案でした。
私たちはこの提案をありがたく受けることが最善と考えました。
そこで先ずは優先的な問題として、孤児院の土地を借りて入られるのは1年ほどとなっていたことから、移転をすることにしたのです。
移転の場所は村長とも相談し、村長の隣りの家が空き家だったことから直ぐに決まりました。
孤児院から歩いて5分ですから、生活には支障はありません。
2019年3月に無事に移転することができ、村の人々が100人以上も集まる盛大なセレモニーも行うことができました。
そして多くの子供が身内の元に帰されましたが、中には全く身内がいない子、いても本当に育てることができない家庭、また帰したが戻ってきてしまった子もいました。
約10人のこうした子だけは新しい移転先で生活することになったのです。
現在の進捗はここまでです。
これからも子ども達の生活を第一に、そしてカンボジア政府の方針や指導のもとに、良い関係を構築しながら運営をしていくことが何よりと考えているところです。